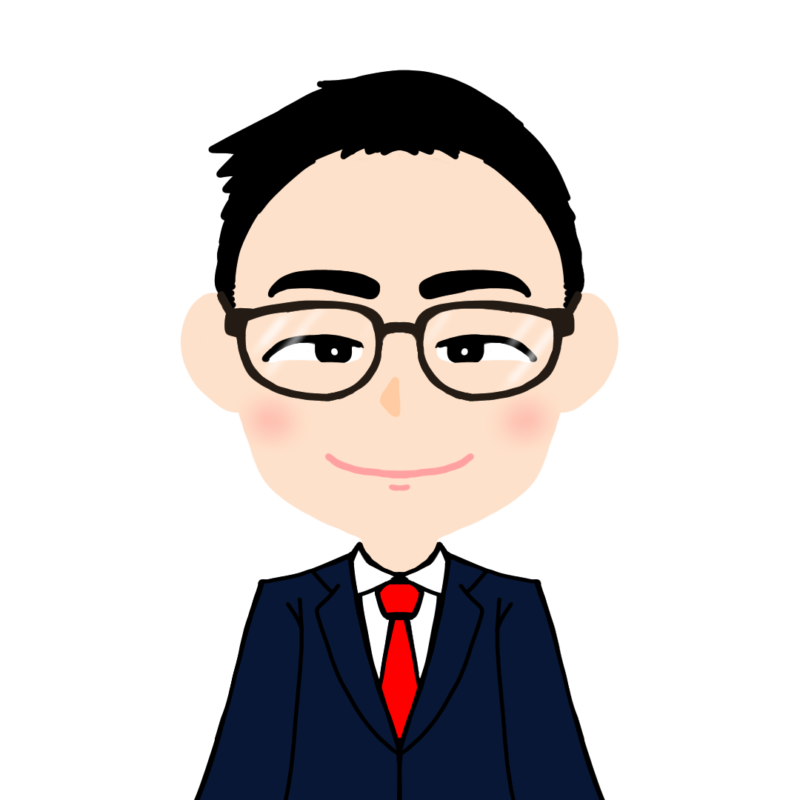観客の心をガッチリつかみ、惹きつけるスピーチをしたいと思っているけど、何かいい方法はないだろうか?
と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
大丈夫です。そんなおいしい方法があるのです。それは、簡単マジックを取り入れたスピーチ方法です。私は、このスピーチ方法をマジックスピーチと呼んでいます。
みなさんが思うより、簡単にできてインパクトのあるマジックはたくさんあります。スピーチ内容に、マジックの現象による効果がプラスされることによって、観客の心をつかみ、惹きつけるスピーチが可能になるのです。
しかし、やみくもにマジックをやればいいのではありません。スピーチの前に「どのように」マジックをするのかについて、時間をかけて具体的にイメージをふくらませて構想するかが大事なのです。
この記事を読んでいただければ、マジックを使って、観客の心をつかみ、惹きつけるスピーチをするために事前に構想すべき4つのポイントがわかります。

観客の心をつかみ、惹きつけるスピーチにするための構想の重要性
スピーチにおいて一番大事なことは、一番伝えたいメッセージを、どれだけ観客の心をつかみ、惹きつけられるかにかかっていると言っても過言ではありません。
マジックはそのためのツールとして使わなければなりません。マジックの現象は強烈であるが故に、容易に観客の心をつかみ、驚かせたり笑顔にさせることができます。
しかし、その反面、メッセージを伝えることよりも、マジックの現象による観客の驚きや笑顔が目的になってしまうことがあります。つまり、観客はマジックを見て喜んでいるものの、大事なメッセージは伝わっていないという事態が起こってしまいます。
そういう事態を避けるためにも、構想段階で「どのように」マジックの現象を利用するのかを考えておかなければならないのです。

マジックを使ったスピーチの4つの構想
実際にマジックスピーチを行う前に私が必ず考えていることが次の4つです。
- 「どのような」マジックがふさわしいのか
- 「どのような」演出をすると最大限の効果を発揮するできるのか
- 「どのような」効果をスピーチの中で狙うのか
- 「どのように」観客からは見えるのか
それでは、これらについてもう少し具体的に紹介していきましょう。
マジックの種類(どのようなマジックを?)
そのスピーチでどのようなマジックを演じるのかを考えることは,マジックスピーチの根幹の部分です。そして、構想のスタートは常に「スピーチのメッセージを有効に伝えるため」であるべきです。そこをしっかりと押さえておけば、独りよがりの演技となることはありません。
具体例をお話しします。あるスピーチで「華やかな未来を築くためには、今『この瞬間』を大事にしてほしい!」というメッセージを伝えたいのであれば、「今」と書いた小さなハンカチを手に入れてもんでいくと「虹色のハンカチ」に変わるという演技などが考えられます。
また、瞬間を小さな紙に例えて、あわせて広げると華やかなイラストが描かれたに大きな紙に変化するなどもいいでしょう。
つまり、観客の心の中でマジックの現象とこちらの伝えたいメッセージが一致するというという体験を創り出すマジックを演じるべきなのです。

マジックの演出(どのようにマジックを?)
マジックは演じ方が重要です。どんなに素晴らしいマジックでも、演出が十分に練られていなければ効果は半減します。演出とは、マジックの現象を効果的に見せる動きや表現、これから起こることに対する観客の期待感を高めていく手段とでも言えるでしょうか。それをスピーチの中で何段階か用意しておくとより効果的です。
例えば、先ほどの例でいくと、ポケットからヨレヨレした「今」と書かれたハンカチがスピーチの中で何回かにわたって出てきます。その度に、「今」ってちっぽけですよね!と言いながらテーブル置いたり、手に持ったりします。
観客は、何のことやらわかりません。しかし、枚数が増えるごとに「なんだこれは?」「何かあるのか?」と考えて徐々に期待感を高めていきます。時間差を使って、観客の心を誘導していく方法です。最終的に、小さいハンカチを集めて、大きい虹色のハンカチに変えます。
これは演出の一例です。様々な演出を組み合わせることによって、より、効果的なマジックスピーチになることは言うまでもありません。

マジックの効果(どのような効果を狙う?)
演じるマジックによってどんな効果があるのかについて事前に構想するのも重要です。
私は、マジックの直接的な効果と間接的な効果を使い分けることが重要だと考えています。
直接的な効果というのは、スピーチのメッセージとマジックの現象が一致している場合です。例えば、「虹色の未来が現れるでしょう」の部分で虹色のハンカチがでてきたり、「たくさん花が咲き誇るでしょう」のところでたくさんの花が出現するなどがそれにあてはまります。

しかし、全てのメッセージをマジックで直接的に表現するのは困難です。そういう場合は、間接的な効果を考えます。例えば、「人間の心はあまのじゃくです」の表現を花の色がどんどん変わるとか、ボードをひっくり返すたびに違う模様になっているとかがそうです。
直接的な効果は、クライマックスにも使えて効果抜群です。間接的な効果は、それ一つではクライマックスとしては少し弱さはありますが、序論、本論の部分で効果的に組み込むことによって、結論に向けての論旨をうまくつなぎ、結論に向けての効果的な盛り上げ役となりうるのです。
この2つの効果をうまく組み合わせることによって、スピーチのメッセージがより効果的に伝わります。
マジックの見え方(どのように見えるのか?)
マジックスピーチを始めてからしばらくは「観客からどのように見えるのか」という視点は私にはありませんでした。しかし、実践を踏むにつれて「マジックは成功し現象もはっきりしているのに、観客の反応が今ひとつ」という場面に出くわすようになりました。
これはどうしてだろうかと考えた結果、演技も演出も、マジックをする状況もタイミングも自分本位であったことに気づきました。つまり、観客がリラックスしやすい状況をまずつくっておくことや、何のために会場に来られているのかをはじめ、観客の事情や状況にもっと気を配らなければならなかったのです。
具体的には、集会で説教をされていた生徒達は、次にマジックを見ても拍手をしたり声を出したりしてもいいのかわかりません。受検の生々しい話を聞きに来ている保護者も同様です。そんな観客側の視点をもつことによって、もっと効果的に伝える方法や演出、雰囲気をほぐす方法、マジックを演じるタイミングなどを工夫できるようになるのです。

構想不足が原因で起こった失敗
自己中心的なマジックと演出
「このマジックをしたい」という自分の欲求からスタートした場合は失敗しやすいです。
特に「見栄えのいいマジックを覚えたばかり」のときは、観客からどのように見えるかという視点が欠け、さらに「このマジックを見せたい!」という強い欲求が勝ってしまい、スピーチのメッセージとの整合性が不十分になりやすいのです。
特に、トランプやコインなど細かいテクニックを必要とするマジックほど、それに陥りやすい傾向があります。自分の技に酔ってしまうのです。きっと「どや顔」になっており、観客も不愉快に感じるケースもあるでしょう。

マジックが主役になってはならない
「構想」があいまいなままでは、スピーチのメッセージよりもマジックばかりが目立ってしまうことがあります。終わった後、観客はどんなことを考えているのでしょうか。きっと「あの人、マジックしたかったんだね」とか「一体,何を伝えたかったんだろう?」というような思いをもって帰途につくのではないでしょうか。
マジックスピーチをはじめて間もない頃、スピーチの最後に大きなくす玉を出したことがありました。自分ではクライマックスのつもりで演じたのですが、メッセージとのつながりが弱かったんですね。思ったほどの拍手はもらえませんでした。
しかも、帰りがけに、「先生、あれ(くす玉)どんな意味だったんですか!」と言われ、がっくりした経験があります。
観客や状況にマッチさせる
「観客が何を聞きたくてこの会場にわざわざ足を運んでいるのか?」「今日のスピーチの内容から観客の雰囲気はどうなのか?」という視点は絶対に考えておかなければなりません。それによって、絶対はずしてはいけないメッセージがあるのです。
また、浮ついた雰囲気が敬遠されるスピーチの場合もあります。そんなとき、会場の雰囲気を徐々に徐々に解きほぐしていく作業が必要となります。十分にほぐれていないと判断したときは、「マジックをしない」という判断も必要かもしれません。

そして、次回への前振りとして、最後に「みなさん、どこかでマジックするか期待していました?ちょっと今日の雰囲気ではマジックする勇気はもてませんでした」などと話してみます。その時の、反応が好意的な感じならば、次回は、ほぐしの作業をしながらマジックを演じることも可能でしょう。
まとめ
この記事では、マジックスピーチをする上での「構想」の重要性について説明しました。マジックスピーチで行うマジックの現象は強烈です。それだけに構想段階で「どのように?」を確認しておかなければ、観客に間違ったメッセージを与えることになります。事前に構想しておくべき点をまとめると以下のようになります。
- どのようなマジックをセレクトするか
- どのような演出をするか
- どのような効果を期待するのか
- 観客からはどのように見えるのか
この記事を参考にして、簡単マジックを使って、観客の心をつかみ、惹きつけるスピーチをあなたも体験してくれるとうれしいです。